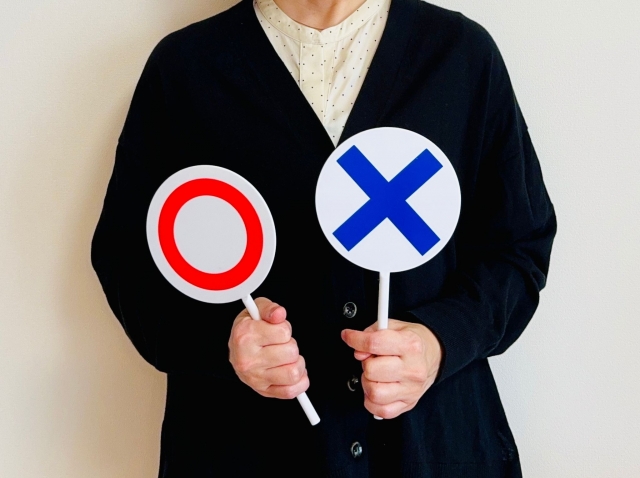社員同士の「派閥意識」をなくすための工夫 ―M&A後の組織融合を成功に導く「心理的統合」マネジメント―
news

- お知らせ
- コラム
はじめに:M&A後に起こる“見えない分断”
M&A(合併・買収)後の統合プロセスにおいて、最も厄介で目に見えにくい課題の一つが「派閥意識」です。
経営統合が形式上完了しても、従業員の間ではしばしば「旧A社の人」「旧B社の人」という無意識の壁が生まれます。
この派閥意識は、直接的な対立や衝突として表れるだけでなく、日常業務の中での小さな「違和感」や「距離感」として積み重なり、やがて組織全体の生産性・モチベーションを低下させる要因になります。
では、なぜ派閥意識が生まれ、どうすれば解消できるのでしょうか。
本稿では、心理学・組織行動学の知見を踏まえつつ、M&A後の組織における“人の融合”を成功に導くための具体的な工夫を解説します。
第1章 派閥意識はなぜ生まれるのか?
1. 「帰属意識」が人間の自然な防衛反応
人は誰しも、自分の属する集団に対して強い帰属意識を持ちます。
社会心理学では「内集団バイアス(In-group bias)」と呼ばれ、「自分の仲間を好ましく感じ、他集団に対して距離を置く」傾向が知られています。
M&Aによって異なる企業文化が一つの組織に融合すると、従業員は無意識のうちに「自分たち」と「相手側」を区別し、旧会社同士の比較意識が強まるのです。
2. 経営陣や上司の言動が派閥を助長することも
統合初期の段階で、どちらの出身者が重要ポジションを占めるかは、社員にとって極めて敏感な問題です。
たとえば「旧A社出身者が管理職を独占している」「旧B社の人ばかり昇進している」といった印象が広がると、実際の意図に関わらず、“見えないヒエラルキー”が形成されてしまいます。
経営トップや幹部が公平な姿勢を明確に打ち出さないと、派閥意識は組織内で定着していきます。
3. 業務プロセス・制度の違いも壁を生む
旧会社ごとに異なる就業ルール、報酬体系、評価制度、コミュニケーション習慣などが残っていると、「私たちのやり方」と「相手のやり方」の違いが日常的な摩擦を生みます。
これは単なる手続きの問題ではなく、企業文化の違いが顕在化しているサインです。
第2章 派閥意識がもたらす組織的リスク
1.報共有の断絶
部署間・グループ間で情報が滞り、業務連携が非効率化します。
2.優秀人材の離職リスク
“どちら側にも属せない中立層”が疎外感を覚え、転職するケースが増えます。
3.顧客対応のばらつき
営業・サービスなど対外的業務で旧体制の癖が残り、顧客に混乱を与えることも。
4.新しい企業文化の醸成が停滞
旧来の価値観が残り続けることで、統合による相乗効果(シナジー)が発揮できません。
派閥意識は、単なる人間関係の問題ではなく、組織競争力を削ぐ経営リスクなのです。
第3章 派閥意識を和らげるための実践的アプローチ
1. 経営トップが“融合”の姿勢を示す
最も効果的なのは、トップ自らが「融合の象徴」として行動することです。
トップメッセージでは、「どちらが上か」ではなく「新しい会社を一緒につくる」ことを強調します。
例えば:
「旧A社でも旧B社でもなく、“新しい私たち”をつくっていこう」
「これからは出身に関係なく、成果と姿勢を重視する」
といった言葉を、繰り返し発信することが重要です。
2. 共通の「新しい目標」を設定する
人は、共通の目的に向かうときに初めて一体感を持ちます。
旧体制の延長ではなく、「統合後の新しい挑戦目標」を設定し、全社員が同じ方向を向けるようにします。
具体例:
「統合1年目の顧客満足度No.1達成」
「地域社会貢献プロジェクトの共同実施」
「新ブランド立ち上げチームの混成編成」
など、“チームの垣根を越えた成功体験”を設計すると効果的です。
3. クロスチーム・混成プロジェクトの推進
派閥意識を最も自然に解消する方法は、「一緒に働く」ことです。
部署横断型のタスクフォースや、旧A社・旧B社混成チームを積極的に編成することで、メンバー同士が「出身よりも目的を共有する仲間」として関係を築けます。
また、ワークショップ形式の課題解決活動(例:改善提案コンテスト)は、部門間の壁を取り払ううえで有効です。
4. 公平な人事制度と評価ルールの明確化
不公平感は派閥意識の温床です。
給与体系・評価基準・昇進ルールを早期に統一し、「透明性の高い制度」に切り替えることが求められます。
経営側は、“旧会社の流儀”を優先するのではなく、両社の良い部分を融合した新ルールを再設計することが理想です。
5. 双方向コミュニケーションの促進
派閥意識の背景には、相互理解の不足があります。
経営層からの一方的な説明ではなく、現場からの意見・感情を吸い上げる機会を設けることが必要です。
例:
統合後100日間の「オープンミーティング」制度
匿名アンケートによる現場意識調査
幹部と現場社員の「意見交換昼食会」
こうした場が、心理的な壁を和らげ、社員の“納得感”を高めます。
第4章 心理的統合を支えるリーダーシップ
1. 管理職の姿勢が組織文化を決める
M&A後の統合期において、現場リーダー(課長・部長クラス)は「文化の翻訳者」です。
経営方針を現場に伝え、両組織の価値観を橋渡しする役割を担います。
リーダーが出身組織に偏った態度を見せると、派閥意識は瞬く間に強化されます。
逆に、リーダーが公平な判断を貫けば、自然と社員も新体制に順応します。
2. “心理的安全性”の確保
異なる出身者が安心して意見を言える環境をつくることが、統合期には特に重要です。
批判や失敗を恐れずに発言できる職場では、派閥よりも「協働」の文化が育ちます。
→ 対話を促進する1on1ミーティングやチーム内での振り返り会議が有効です。
第5章 まとめ:派閥を「融合エネルギー」に変える
派閥意識は、見方を変えれば「異なる価値観を持つ人たちが共にいる」状態でもあります。
つまり、対立の裏には多様性のポテンシャルが隠れているのです。
経営者や幹部が適切に方向付けすれば、派閥意識を「新しい組織文化を生み出す力」に変えることができます。
統合の成功とは、「どちらの会社が勝つか」ではなく――
「全員が“新しい会社の一員”であると実感できるかどうか」です。
派閥をなくす最善の方法は、共通の成功体験をつくること。
そのために、対話・公平性・共創の仕組みを整えることが、経営の最重要課題なのです。
※弊社へのご相談はお電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。