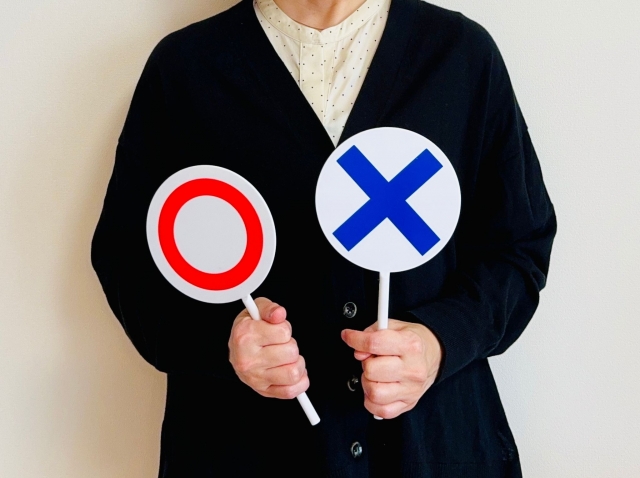株式譲渡と事業譲渡:中小企業が選ぶべき手法とは?
column

- コラム
はじめに
中小企業がM&Aを検討する際、最も重要な論点の一つが「株式譲渡」と「事業譲渡」のどちらの手法を選ぶかです。どちらも企業の経営権や事業を第三者に移転させる方法ですが、そのスキームや法的な取り扱い、税務上の影響、従業員・取引先との関係などに大きな違いがあります。
中小企業の場合、規模や資本構成、後継者の有無、事業の特性などによって最適な手法は異なります。本コラムでは、株式譲渡と事業譲渡の基本的な仕組みを整理し、それぞれのメリット・デメリットを詳細に解説したうえで、中小企業がどのように選択すべきかを考えていきます。
1. 株式譲渡とは
株式譲渡は、会社の株主が保有している株式を譲渡することで、買い手に経営権を移す手法です。会社そのものの法人格や契約関係、資産・負債はそのまま存続し、株主だけが入れ替わるという仕組みになります。
特徴
法人格がそのまま残る
資産・負債・契約・許認可も包括的に承継
取引先や従業員との契約を改めて結び直す必要がない
売り手にとっては「株を売る」だけで完結しやすい
中小企業では、株主=オーナー経営者であるケースが多く、株式譲渡は経営権の承継をシンプルに行える方法といえます。
2. 事業譲渡とは
事業譲渡は、会社が営んでいる事業の一部または全部を選択的に譲渡する方法です。譲渡対象の資産・負債・契約関係を個別に特定し、必要なものだけを買い手に移転させることができます。
特徴
売り手法人は存続する
譲渡対象を選択できる(資産や契約を取捨選択可能)
個別の契約移転手続きが必要(従業員の同意、取引先の承諾、許認可の再取得など)
売り手にとっては、不要な負債やリスクを切り離すことができる
事業譲渡は複雑な手続きを伴いますが、買い手・売り手双方にとってメリットがあるケースも多いです。
3. 株式譲渡のメリット・デメリット
メリット(売り手側)
株を譲渡するだけで済むため手続きが比較的簡単
契約や従業員関係が維持されるため、取引先への影響が少ない
売却益は株主個人に帰属するため、資産形成につながる
メリット(買い手側)
既存の事業体をそのまま引き継げる
許認可やライセンスも承継できる場合が多い
従業員や取引先の関係性を維持できる
デメリット(売り手側)
負債や潜在的なリスクも包括的に引き渡すことになるため、買い手の交渉力によっては価格が下がる
譲渡益課税(株式譲渡益に20%程度)が発生
デメリット(買い手側)
過去の債務や訴訟リスクも承継してしまう
デューデリジェンスでのリスク洗い出しが必須
思わぬ偶発債務が後から発覚する可能性がある
4. 事業譲渡のメリット・デメリット
メリット(売り手側)
不要な事業や負債を切り離せる
主力事業を売却し資金を得た後、別事業で会社を存続させることも可能
分社化や整理の一環として柔軟に活用できる
メリット(買い手側)
必要な資産・契約・人材のみを取得できる
不要な債務や訴訟リスクを回避できる
買収規模を柔軟に調整できる(事業の一部のみ取得可能)
デメリット(売り手側)
個別契約の承諾が必要で手続きが煩雑
従業員の同意が必要であり、移籍に反発が出る場合がある
譲渡益は法人に帰属し、法人税課税の対象となる
デメリット(買い手側)
契約や許認可を新たに結び直す必要があり、承継に時間とコストがかかる
顧客や従業員が離反するリスクがある
統合プロセスが複雑化する可能性がある
5. 税務面での違い
税務は、手法選択に大きな影響を与える要素です。
株式譲渡:売却代金は株主個人に帰属し、譲渡所得課税(約20%)が適用される。法人株主の場合は法人税の課税対象。
事業譲渡:譲渡益は会社に帰属し、法人税(約30%前後)が課税される。さらに株主が会社から配当を受け取れば、二重課税となるケースがある。
売り手オーナーにとっては、税負担の観点から株式譲渡が有利といわれることが多いです。
6. 中小企業が手法を選ぶ際のポイント
(1) 事業承継目的なら株式譲渡が有利
後継者不在で会社を丸ごと引き継いでほしい場合、株式譲渡が適しています。手続きがシンプルで、従業員や取引先への影響も小さいため、事業承継型M&Aの定番手法です。
(2) 不採算事業の切り離しなら事業譲渡が有効
複数事業を展開している場合、赤字事業のみを売却して会社全体の体質を改善するなど、事業再編の目的で事業譲渡が使われます。
(3) 許認可や契約関係の重要性を考慮
規制業種では、許認可の承継が困難な場合があり、その場合は株式譲渡が適していることが多いです。逆に、不要な負債や過去のリスクを抱えた会社の場合、事業譲渡の方が安全です。
(4) 税務・会計の影響を試算
オーナー個人の資産形成を重視するなら株式譲渡、会社全体の資金調達や再編を重視するなら事業譲渡、といった観点で選択することも重要です。
7. 専門家との連携の重要性
株式譲渡と事業譲渡の選択は、経営戦略・法務・税務が複雑に絡み合うため、経営者だけで判断するのはリスクが高いです。M&Aアドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、中小企業診断士などの専門家と連携することで、最適なスキームを設計できます。
おわりに
「株式譲渡」と「事業譲渡」はどちらも中小企業のM&Aにおいて活用される代表的な手法ですが、その目的や状況によって適否は異なります。事業承継型であれば株式譲渡が主流であり、再編型であれば事業譲渡が有効といえるでしょう。
重要なのは、単なるスキームの比較ではなく、経営者自身の目的、会社の状況、税務・法務上の影響を総合的に判断して選択することです。専門家とともにシナリオを検討し、最もメリットを享受できる手法を選ぶことが、中小企業M&A成功の鍵となります。
弊社へのご相談はお電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。