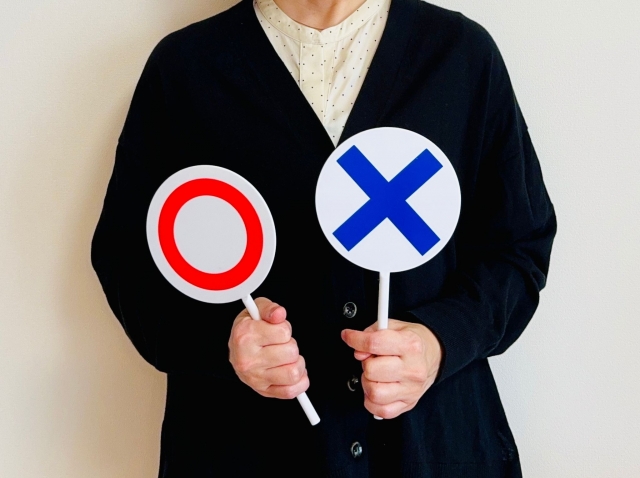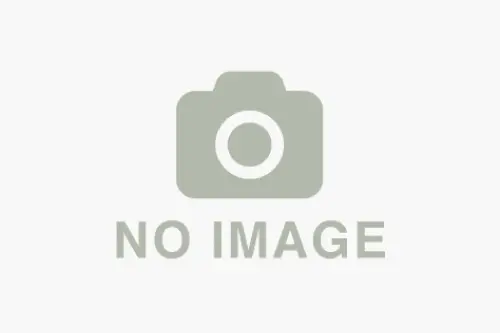LOI(基本合意書)のポイントと注意点 ―M&A成功の“分岐点”となる初期合意の設計とは―
column
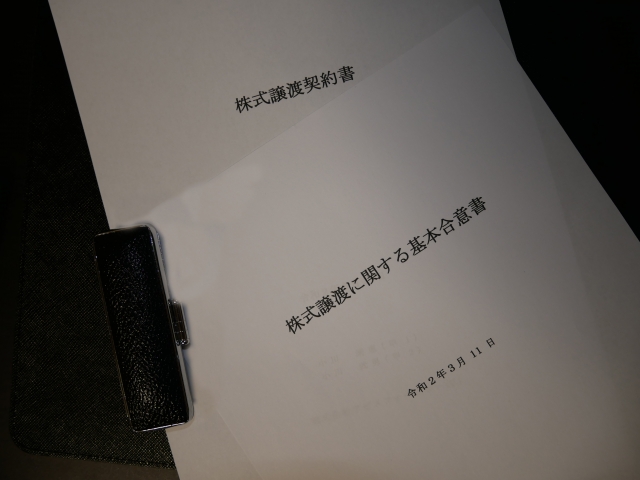
- コラム
―M&A成功の“分岐点”となる初期合意の設計とは―
【はじめに】基本合意書(LOI)とは何か?
M&A(合併・買収)のプロセスにおいて、買い手と売り手が本格的な交渉を始める前に、その枠組みや基本的な条件について合意するのが「基本合意書(Letter of Intent:LOI)」です。LOIは、将来の正式契約に向けた“方向性の一致”を確認するための文書であり、ビジネスにおけるいわば「結婚前の婚約」にあたるものと言えます。
LOIは法的拘束力のない文書と思われがちですが、実際にはその中に拘束力を持つ条項(独占交渉期間、秘密保持義務など)が含まれることが一般的であり、慎重な検討と明確な設計が求められます。
本稿では、LOIの目的と構成要素、注意すべきポイント、そして買い手・売り手双方の立場から見た戦略的な活用法について、実務レベルで深掘りします。
【第1章】LOIの目的と役割
M&A交渉における“マイルストーン”
LOIは、M&Aプロセスの中間地点に位置づけられる重要な文書です。次のような目的を果たします:
1.基本条件の整理と合意
株式譲渡価格や支払い方法などの経済条件を含めた「基本線」の一致を確認する。
2.デューデリジェンスの起点
買い手が本格的な企業調査(DD)を行う前提として、LOIで一定の合意があることが信頼の証となる。
3.交渉の“独占性”確保
他の買い手と並行交渉をされないよう、一定期間の独占交渉を求める。
4.最終契約書(SPA)への布石
最終的な株式譲渡契約書や事業譲渡契約書の内容を構築するための基盤。
【第2章】LOIの一般的な構成要素
LOIには、以下のような要素が含まれるのが一般的です。条項の内容や拘束力の有無は案件ごとに異なるため、個別の文脈に即した検討が不可欠です。

【第3章】LOIにおける重要ポイント
1. 譲渡価格とバリュエーションの曖昧さに注意
LOIに記載される価格は、あくまで「基本的な合意」にすぎず、デューデリジェンスの結果によって変更される可能性があることを前提とすべきです。特に中小企業M&Aでは、財務情報の精度や過年度決算の特殊性から、バリュエーションが変動しやすい傾向にあります。
【留意点】
-
「価格は最終的なDD結果を踏まえて再協議する旨」を明記
-
「EBITDAの●倍」「純資産+営業権●円」といった算定根拠を記載すると良い
2. 拘束力の明示と曖昧さの排除
LOI全体が法的拘束力を持つと誤解されることがあります。あくまで「法的拘束力を有する条項」と「有しない条項」を明確に区別し、文書上にも明記しておく必要があります。
【例】
-
「本書のうち、第5条(秘密保持)、第6条(独占交渉権)及び第8条(準拠法・合意管轄)を除き、その他の条項は法的拘束力を有しない。」
3. 独占交渉期間は短すぎず、長すぎず
独占交渉権を設定する場合、期間設定が重要です。一般的には2~3ヶ月程度が多く、買い手は安心してDDを進められる一方、売り手は市場との接点を一時的に閉じることになるため、慎重な判断が必要です。
4. スケジュールは現実的に設定を
買い手側が強く希望して無理なスケジュールを組むと、社内調整が追いつかず破談となるリスクもあります。M&Aには法務・税務・財務など多方面のプロセスがあり、余裕を持った計画を立てるべきです。
【第4章】売り手側から見たLOI戦略
1. 価格以外の“質”にも注目
買い手の提示価格が高いからといって即決するのは危険です。資金調達力、クロージング実行力、経営理念の相性、従業員雇用の維持など、トータルで判断すべきです。
2. 複数の候補との交渉を継続できるタイミングの見極め
LOIを締結すると基本的に独占交渉状態となるため、他候補との比較検討が困難になります。逆に言えば、「候補先の絞り込みが済んだ段階」でLOI締結に進むのがセオリーです。
【第5章】買い手側から見たLOI戦略
1. LOIで信頼関係の土台をつくる
LOIは単なる書面ではなく、相手企業に対する“誠意”や“交渉スタンス”が問われる場面です。事業承継型のM&Aでは、売り手が感情面を重視する傾向もあるため、礼節と透明性が重要です。
2. DDの自由度確保と協力体制の明示
「必要な情報開示がなされるか」「現地視察・従業員面談が可能か」など、DDの実効性を担保する条文が必要です。LOIで合意が取れていないと、DD中にトラブルが起きやすくなります。
【第6章】トラブル回避のための実務上のアドバイス
1.法務アドバイザーと事前にドラフト作成すること
LOI締結の段階でも、経験豊富な弁護士やFAのサポートが不可欠です。
2.不明瞭な表現は避け、可能な限り定義を明確化
例:「適正な価格」「合理的な期間」といった抽象表現は争点になります。
3.感情的な“急ぎすぎ”を避ける
特に中小企業の経営者間では、初対面での印象やスピード感に引きずられて内容を曖昧にしたままLOIを締結してしまうことも。冷静な判断が重要です。
【まとめ】LOIは“信頼の契約”である
LOIは、M&Aプロセスの中で最初にお互いの「期待値をすり合わせる」場であり、将来の信頼関係と交渉の土台を築く重要な一歩です。価格や条件をめぐって神経を使うことは当然ですが、それ以上に大切なのは、「誠実さ」「透明性」「柔軟さ」といった姿勢を相手に伝えることです。
この初期の“設計ミス”が、その後の交渉全体に影を落とす可能性もあるため、LOIこそ慎重かつ丁寧に扱うべきフェーズなのです。
弊社へのご相談はお電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。
関連記事:StockSun社のコラム
「LOIとは? 締結目的や MOUとの違いから 11の記載内容を解説」も参考にしてください。